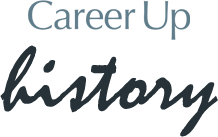~第5章~
成長期②
学会からのアプローチ
「日本スポーツとジェンダー学会」(2002年設立)
証言者:飯田貴子氏(日本スポーツとジェンダー学会)
2002年に創設された「日本スポーツとジェンダー学会」(以下、JSSGS)は、今年で18回大会を迎える。「スポーツにおける男女平等・公平の達成」を目標に掲げてきたこの学会は、単なる学術団体の枠を超え、人びとの偏見や認識を問うためのアクションを起こしてきた学会でもある。飯田貴子氏は、初代会長でもあり、体育・スポーツ系の学会で初めて「ジェンダー」の用語を使って発表した方でもある。

JSSGS立ち上げの経緯について
女性学が日本の大学教育の中で広まっていた頃、飯田氏が教鞭をとっていた私立大学でもその動きが高まり、女性学の関連書籍を読みあさったという。もともとリベラルなご両親の元で育った飯田氏にとって、女性学との出会いはむしろ自然な流れだった。
同僚の授業では「三つ指をついて夫を出迎える」ことを学生に説くような内容もあった。そんな当時、飯田氏にとって女性学の内容は「目から鱗だった」という。そして、性差別や性役割の理由にしばしば挙げられている「女は体力がない」という言説に疑問を持つようになった。その気づきは、病気もせず、仕事はもちろんのこと、家事や育児に関しては夫とは比べものにならないほど関わっているご自身の体験からきたものと言われる。
日常生活の体力に男女差はないのに、体力テストで測った体力だけで「女は体力がない」と言われてしまう。体力テストそのものに、すでにジェンダーが埋め込まれている証だと、1995年の体育学会で発表した。この発表を機に、佐伯年詩雄先生や森川貞夫先生など男性研究者たちも関心を持ってくれるようになり、ジェンダーをテーマに研究を続けて行こうと勇気づけられた。
学会発表をした頃、井谷恵子氏も女性とスポーツの研究会を京都教育大学で行っていた。熊安貴美江氏は大阪女子大学でアメリカのスポーツ史をテーマに研究をしている頃であった。來田享子氏も1920?30年代の女性の競技連盟について書いていた。点在していた研究者たちが、京都での研究会を通じて集まり『目で見る女性スポーツ白書』(大修館書店、2001年)、アン・ホールによるFeminism and Sporting Bodies: Essays on Theory and Practice. (1996)の翻訳本 『フェミニズム・スポーツ・身体』(世界思想社、2001年)を出版することになり、学会への機運が高まっていった。
JSSGSが立ち上がる前、体育学会やスポーツ社会学会でもジェンダーに関わる研究は行われていた。しかし、男性中心の伝統的な分野の研究者がマジョリティを占める中、ジェンダーに関わる重要な指摘を発表してもなかなか受け入れてもらうことはできなかった。そのようなもどかしさも学会立ち上げの原動力につながっていった。2002年1月、飯田氏の誕生日に7名の女性たちが集結し、その年の6月22 日の学会設立までこぎ着けた。
JSSGSのこれまで
学会の予算は潤沢ではなかったものの、会員一人ひとりの能力が高く、研究誌やホームページをはじめとし広報や学会運営のマニュアル化等すべて自分たちの手で作り上げてきたという。もちろん意見の相違等はあったものの、絶対に分断しないよう努力してきたと飯田氏は語る。またジェンダーやフェミニズム、セクシュアリティの研究をしている人は、安い謝金で講演に来てくれたり、謝礼を寄付してくれたりとJSSGSの誕生を喜び応援してくれているようでありがたかった。
JSSGSの認知度をあげるために、男性研究者の他、他領域の研究者、教育関係者、学術団体ではない人たちも巻き込んだ。ヌエック(国立女性教育会館)にでかけ、一緒に研究会を実施したり、JSSGSのオープニングでダンスを披露してもらったりした。ただ、バリバリ仕事をこなしている人であっても、主婦業を女性の役割として受け入れてきた人たちの中には、セクシュアリティに対してアレルギー反応を示す人も多かったという。
5年ごとの記念大会は、海外の研究者(アン・ホール、グードゥルン・ドルテッパー、トニー・ブルース)を招聘した。また、会員がWSI(女性スポーツインターナショナル)の役員を務め、国際学会、世界女性スポーツ会議等でも発表し、JSSGSの認知は国内よりも先に海外に広まった感がある。
学術組織の役員にJSSGSの会員が入るよう意識的に行動してきたし、断らずに引き受けるという姿勢で臨んできた。また、学会では女性役員を増やすためのポジティブ・アクションに関する議論を継続して行ってきた。その結果、現在、日本体育学会の22名の役員のうち女性が11名、そのうち5名がJSSGS会員となっている。日本学術会議の健康・スポーツ科学分科会でも16名の委員のうち6名が女性で3名がJSSGS会員である。副会長、委員長等の要職を務めていることも特筆すべきだ(いずれも2018年度現在)。学術組織としての誇りは、春季研究会にて学会大会の基調講演やシンポジウム等の登壇者の文献抄読を行い、学会に臨むことである。この活動は、次世代研究者の育成にも繋がっている。
「女性スポーツ」に関わる政策に対して
一番悲しいのは、2020問題が「2020東京オリパラ」しか注目されていないことだ。スポーツ行政に関わる人は、「202030」(社会のあらゆる分野において2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とするという政府目標)の達成に強く向かって欲しい。政策では、中学女子や20代女性の運動実施率の向上を問題視していたが、これらは幼少期の遊びやスポーツに影響する社会のジェンダー規範から考えていかないといけない。女性スポーツ政策は、託児所を作ればいいという話ではないはずである。
男女共同参画基本計画で書かれていることは、スポーツ基本計画に組み込まれるべきである。縦割り行政でなく、視野を広げて女性とスポーツを捉えて行かないとスポーツ界だけが取り残されていく危険性があると飯田氏は言う。また「女性スポーツ」とひとくくりにしない視点も、そろそろ必要なのではないか。特にセクシュアリティは、身体が前面にでるスポーツ領域ゆえにセンシティブで重要な問題である。政策は、主流から外れていく人をいかに救い上げていくかということをもっと議論して行かなければいけない。
将来に向けて
マズローは欲求五段階説の一番上に自己実現の欲求を唱えている。だが、スポーツ社会学を専門とする者は、政治的思想をもって社会変革をすることが欲求の最上級につながるべきだと飯田氏は考えている。このような考えは、理論と実践の両方が必要であるという女性学を牽引してきた人たちや、アン・ホールの考えにもとづく。
今後は、ジェンダー視点だけでなく、セクシュアリティ、人種、階級、障害、地域等の変数も捉えていかなければいけない。またJSSGSでは東京2020に対しても、反五輪を訴える立場から、開催が決まった今だからこそ変革のチャンスであるという立場まで、さまざまある。いろんな議論があっていい。それらの議論から、スポーツ文化の再構築を目指したい。女性の中にも違いや異なる考えがあるんだということにみんなが気づいていくことにJSSGSが貢献できればいいなと思う。
 取材後記
取材後記
 取材後記
取材後記ここには書ききれないほど、いい意味でさまざまな話に脱線し、引き出しの多い飯田氏と充実した時間を過ごすことができた。なかでも「子どもは女性1人で育てるものではない、社会で育てるのよ」と発した飯田氏の言葉が、卒業生の人生に大きな影響を及ぼしていたというエピソードは大変興味深かった。大学卒業後は、主婦になることが当たり前だった飯田氏の学生時代に、働く女性のロールモデルはほとんどいなかった。しかし学生たちにとって飯田氏の存在は、大学の教員でありながら良きアドバイザーであり、ロールモデルだったようだ。大学で働く者として、発した言葉の影響力とロールモデルとしてあることをあらためて実感した。
学術分野でスポーツとジェンダーの道を切り開いてきたJSSGS。すでに17年の蓄積ができたことに敬意を表したい。同時に、課題が山積しているスポーツとジェンダーの領域に、私自身はどのように関われるのかと自問する機会をいただいた飯田氏にもお礼を言いたい。
山口理恵子(城西大学 女性人材育成センター所長、経営学部 准教授)